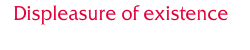昔の仕事さ
飯盛女により最も繁栄した宿場町「品川宿」
宿場町として東海道第一の規模を誇っていた品川。交通上で重要な地位を占め、特に近世初頭より急激に発展していった。江戸時代の文献によると、御殿山下から品川宿までの一帯はすべて海浜の洲で、古い街道は現在の東海道線よりやや西を走り、矢口村から新井宿(大田区)を経由し、居木橋の一町ほど下にて目黒川を渡って下高輪方面へと繋がっていたと考えられている。
東海道の多くの宿場は、元々は平安もしくは鎌倉時代より街道の集落であり、品川も戦国時代から南品川と北品川とに分かれて宿の形をなしていた。ただし、近世の品川宿が戦国期以来の宿を継承してできたものか、あるいは新たに屋敷割を行い、人工的な区画によってできたものであるかどうかは定かではない。とはいえ、関ヶ原の合戦後、全国統一をなした徳川家康が江戸と全国を結ぶ道路網の整備に着手した慶長六年(一六〇一)には、東海道が海ばたを通るようになり(東海道の各宿には幕府より家康の伝馬朱印状と伊奈忠治次、彦坂元正、大久保長安の連署による「御伝馬之定」が交付され、伝馬朱印状を携帯していない者には各宿が公用の伝馬を出すことが禁じられた)、品川宿も東海道に沿って形成されていったことは間違いなさそうだ。
品川には伝馬朱印状は残されていないが、江戸時代の終わりに地史として編纂された『新編武蔵風土記稿』によると、慶長六年に品川郷を宿駅に指定し、駅馬三十六匹を置かせた代償に五千坪の地子(地税)を免除したと記されている。
東海道第一の宿駅品川は、色街としての顔も持っていた。幕府が江戸四宿(品川・内藤新宿・板橋・千住)の旅籠屋に、飯盛女の名目で遊女を置くことを公認したのは享保三年(一七一八)のことだった。当初は旅籠屋一軒につき二人が定数だったが、繁栄に合わせてその数も増加し、明和元年(一七六四)年には大旅籠九軒、中旅籠六十六軒、小旅籠十八軒に対し、品川宿全体で五百人もの飯盛女が許された。品川を除く三宿では百五十人しか許可されなかったことからも、いかに東海道が人の往来が盛んであったかを証明している。この員数は幕末まで変わることなく続き、実際に常時千人を超える飯盛女が遊女として営業していたともいわれている。つまり、色街としての繁栄が、品川宿の町としての発展に繋がったともいえよう。
加えて品川宿自体も、御殿山の桜、潮干狩り、海晏寺の紅葉など、江戸では屈指の名所であり、品川宿の繁栄は芝三田薩摩屋敷の武士や増上寺の僧侶をはじめ、江戸っ子がわざわざ出かけることによって維持されていた。参勤交代における大名の通過で莫大な利益があったであろうと想像するのは間違いで、参勤交代では一切の入用な物は持参して出発していたため、いくら大名が通過するとはいえ利益は思ったほどではなく、品川宿では再三再四幕府に下賜金を願い出るほどであった。
鬼平の提案で無宿者・軽犯罪者の更生施設「人足寄場」が置かれた石川島
隅田川に架かる佃大橋から石川島を望むことができる。元は隅田川河口に堆積した三角州だ。この島に火付盗賊改役長谷川平蔵の建議により、幕政改革の一環として江戸に流入した無宿者や軽犯罪者を強制的に収容させ、更生を促した人足寄場が設置されたのは、寛政二年(一七九〇)のことだった。
江戸で無宿者が増加し始めたのは宝暦の頃からだろうか。当初は無宿者は佐渡ヶ島の金鉱へ人足として送り込まれたが、後には浅草にあった無宿者の収容所である非人溜へ送られていた。が、寛政の改革の頃には非人溜でも増加の一方をたどる無宿者を収容しきれなくなり、そこで長谷川平蔵は授産所を兼ねた施設を作ることを提言した。
寄場人足の小屋は六房に分かれ、罪科の軽重によって各房があてがわれた。人足の逃亡を防ぐため房は牢獄の造りになっていたという。また、老人や病人、婦女は別に各一室を設けて収容した。人足には米つき、縄ないなどの単純労働に従事させた他、各自に手工を営ませ、紙すきや炭団の製造なども行われた。
当初の収容人数は百三十人程度であっただろうか。が、次第にその数を増し、天保改革以後は無宿者のみならず、江戸払以上追放の者までもが寄場に送られたため、収容者は五百人を超えるに至っている。また、寄場内での規則も厳しく、盗みや博打を行ったものは死罪とする罰則が設けられていた。
改悛が見られ、身寄りの者から引取が願いだされた人足は、復帰後の営業資本として銭五貫文から七貫文を渡されて出所を許された。しかし、その人数は寄場人足の半数にもならず、また寄場を出たところで、結局は正業に就けずに元の生活へと逆戻りする例が続出したとの話もある。
その後、寄場は明治時代に突入すると、新政府の鎮台府所属となり、明治三年(一八七〇)になって廃止された。跡地は犯罪者の懲役場へ転用され、明治十年(一八七七)には警視庁監獄署となった。一般の人々からは石川島監獄署と呼ばれ、巣鴨に新たに監獄署が完成した明治二十八年(一八九五)まで存続した。
ところで、石川島は日本最初の洋式造船所が建設されたところでもある。嘉永六年(一八五三)、幕命を受けた水戸藩によるものだ。安政三年(一八五六)には洋式木造帆船旭日丸、慶応二年(一八六六)には蒸気軍艦千代田形などが造られている。明治維新後は官営による造船所となったが、明治五年(一八七二)に廃止、その跡地の払下げを受けた旧幕臣平野富二が石川島平野造船所を個人で創業させている。そして昭和三十五年(一九六〇)、播磨造船所と合併して石川島播磨重工業設立、昭和三十七(一九六二)には新造船発注高で国内最大の地位を得たが、造船不況の波を受けて昭和五十三年(一九七八)に工場は廃止された。なお、跡地は再開発され、現在は高層マンション群が建ち並んでいる。
現在の中央区で生まれ、幕府の命令によって台東区へ移動となった公認遊郭「吉原」
享保三年(一七一八)、江戸で最初の人口調査が行われたところ、男約三十九万人、女約十四万人、合計約五十三万人。江戸の町づくりが進み、全国各地より江戸へ人々が移住するようになったが、大半は男であり、その傾向は天保期まで続いた。しかも先の数字は町方だけのもので、諸大名においても参勤交代の際、各大名は妻子を江戸に置いて住んだものの、家臣は単身赴任であったため、やはり江戸には男が多く集まったといえる。
そんな江戸において、女の町が存在した。そう、遊郭として名を馳せた吉原だ。慶長(一五六九~一六一四)の頃、江戸には麹町と鎌倉河岸に十四、五軒、大橋内柳町に二十軒余の遊女屋があったが、慶長十七年(一六一二)、遊女屋の主人を代表して庄司甚右衛文が幕府に江戸に一ヶ所公認の遊郭の許可を願い出た。
「京都や大阪、駿府、その他全て繁華な都市には遊郭が公許されているが、江戸には公認の遊郭がなく、所々に分散しているのは江戸のためによくないことだ」
以上の理由による。そこで幕府は元和三年(一六一七)、吉原以外での遊女屋営業を禁止しするなど五項目の条件を付し、葺屋町の東側一帯に遊郭開設の許可を与えた。そして元和四年(一六一八)に遊郭が完成、葭が生い茂る野原に造られたことより葭原と命名され、後に吉原と改められた。
吉原が江戸で唯一、公認された遊郭と認められて以来、吉原以外で営業する遊女は隠売女と呼ばれ、常に取締りの対象となった。しかも吉原の遊女屋には、隠売女を置く店の摘発権を与えられていた。実際、江戸中期以降、吉原の他にも岡場所と呼ばれる隠売女を抱えた遊女の町が江戸の各所で繁盛していたが、多くが廃止されるに至っている。
さて、江戸が繁栄するようになると、江戸城に近かった吉原が江戸の中心地となるのを避けるため、明暦二年(一六五七)、幕府は吉原に浅草日本堤への移転を命じた。旧地の葺屋町は元吉原と呼ばれ、翌年移転を完了し、再び営業が開始された新たな遊女町は新吉原と名付けられ、それまで禁止されていた夜間営業も許されることになった。以後、この新吉原は、売春禁止法が施行される昭和三十三年(一九五八)までおよそ三百年もの間、存続した。
新吉原へ通うには、隅田川を猪牙船で上るか、駕籠や馬で行く手段、あるいは日本堤を歩いていく方法があった。四囲を遊女がおはぐろを捨て、そのために水が黒く濁ったことから名付けられた鉄漿溝に囲まれ、別世界を築いていた吉原は、時代によって顧客層も変化していった。元吉原および新吉原初期には武士、元禄期には豪商、享保期には特権商人、そして宝暦以降になって一般町人たちも足を運ぶようになった。宮本武蔵もしばしば元吉原へ通い、島原の乱へは吉原の遊郭から出陣したとの逸話も残されている。
交易で賑わった内藤新宿は、甲州街道を行き交う人馬で溢れた宿場町
江戸四宿のひとつ、内藤新宿は元禄十一年(一六九八)年に開かれた宿駅だ。それまで日本橋と甲府を結ぶ甲州街道の最初の宿駅は高井戸に設けられていたが、距離が遠く行き交う人々は難儀していた。そこで浅草の名主喜平兵衛らの願い出により、現在の新宿御苑付近に新たに甲州街道の初宿が置かれた経緯を持つ。一帯は信州高遠藩主内藤氏の屋敷地であり、新しい宿場の意味を兼ねて内藤新宿と称した。やがて街道の両側には、多くの遊郭を兼ねた旅籠屋や茶屋が軒先を並べるようになったという。ところが、享保三年(一七一八)になると、幕府は内藤新宿の廃駅を決めている。
「旅人もすくなく、新宿之儀に候間、向後古来之通宿場相止」(御触書寛保集成)
との理由による。しかし、実のところは飯盛女が増え風紀が乱れたことや、旗本内藤新五左衛門の弟大八が、内藤新宿の茶屋の下男に女のことで殴打された事件が生じ、立腹した新五左衛門が切腹させた弟の首を持参し、自らの知行を差し出すかわりに内藤新宿の廃駅を願い出たためともいわれている。あるいは、幕府の享保の改革の一環であったとの説もある。廃駅に伴い、旅籠屋の多くは一時は転業を余儀なくされたのだった。
その後、新宿界隈は江戸の発展に伴い、甲州、青梅街道を往来する人馬も増加の一途をたどった。そこで宿駅再開の動きも盛んになり、明和九年(一七七二)、内藤新宿復活の運びとなった。再興には冥加金の上納が条件でもあり、幕府の宿場繁栄策や財政政策も大きく関わっていたようだ。
再開後は、岡場所としての復活も著しかった。新開地であるため、江戸の各所より遊女が集まった。やがて旅籠屋には飯盛女を置くことも認められ、その数は一応は千住、板橋なみの百五十人となっているものの、実際には五百人近くになっていたようだ。
一方、内藤新宿では、西郊の農村地帯と江戸とを結ぶものであったため、再開まもない頃には野菜を扱う問屋が既に存在しており、米穀問屋も栄えるようになった。つまり、交易の地としての役割をなしていたことになる。肥桶を付けた百姓馬が頻繁に往来していたため、馬糞の地と蔑称されたこともあるという。
主な運搬物資は、米穀物を筆頭に農村から江戸へは蔬菜が、江戸から農村へは下肥が中心であった。四谷と内藤新宿を境にする地点には江戸城下町の入口を意味する四谷大木戸が元和二年(一六一六)より設置されており、木戸脇には馬改番屋が置かれ、大木戸が廃止される寛政四年(一七九二)まで江戸へ運ばれる物資や人馬を監視する役目を担っていた。内藤新宿を経由する甲州街道は、江戸の五街道の中でも最も利用者が少なかったといわれ、内藤新宿も街道を一歩離れれば薮や雑木林が広がる武蔵野の原野であったが、産業道路としては重要な街道であり、多くの物資が江戸に供給されたのだった。
飯盛女の評価が低かったため、江戸四宿の中で最も静かだった板橋宿
家康が江戸に幕府を開いた慶長八年(一六〇三)、五街道制定にあわせて中山道に首駅となる板橋宿が置かれることになった。江戸より二里半(約十キロ)、宿の長さはおよそ二十町九間(約二キロ)に渡り、宿場内は入口から平尾宿、中宿、上宿に分かれ、中宿と上宿との間に流れる石神井川に架かる小さな板の橋より板橋宿との名が付けられた。
宿場の中心地をなしていた中宿には、問屋場や本陣などの旅籠が建ち並び、旅籠は飯盛女を置く飯盛旅籠と平旅籠とに分類された。また、旅行や物資の運搬には幕府が定めた人足や馬数の他、荷物の重量も定められており、その規定は板橋の南東に置かれた高札場に高札として掲げられ、問屋場に併設された貫目改所にて検査が行われていた。幕府が定めた規定より重い荷物は過貫目と呼ばれ、二個分の料金を払わねばならなかった。
上宿には商人宿や馬喰宿が密集し、宿のはずれには縁切榎の大木が今でも三代目となって残されており、その名称から婿入りや嫁入りの際にはこの木下を通るのを避けたという。孝明天皇の妹、和宮が将軍徳川家茂に降嫁することになり、江戸への下向における行列では、縁切榎は木の根元からこもで包み隠されたとの話が伝え残されている。
寛永十二年(一六三五)、参勤交代が始ってからは大名三十家が往復し、また東海道に比べ川が少ないことから中山道を通る一般の旅人も多く、宿場も繁盛したようだ。板橋宿場に限っては、幕府による宿場の保護、助成政策であった問屋給米や継飛脚給米などが給付されておらず、経済的にも潤っていた宿場だったと推測される。
とはいえ、加賀百万石の前田家、高田十五万石の榊原が通る以外には十万石程度、もしくはそれ以下の大名が通過していたにすぎず、本陣や脇本陣も備えた宿場ではあったものの、品川や千住、内藤新宿のような賑やかさを誇ることはなかった。
「旅送り橋より川が人がふえ」
この川柳は、江戸庶民にとって遊び場には品川の宿場のほうが賑やかで、板橋の宿場は女郎も安っぽく、面白みに欠けたことの意を含んでいる。
さて、板橋宿では、品川宿に次ぐ人数(幕府より公許されたのは百五十人)の飯盛女が旅籠屋に置かれていた。護国寺門前にあった音羽の岡場所の賑わいが板橋にまで及んだようだ。「岡場所遊郭考」によると、天保十三(一八四二)から遊女が六畳から八畳ほどの板間であった見世に並び、顔見世を行い道行く客を誘っていたという。板橋と千住では吉原にならって顔見世をしたが、品川、内藤新宿では全員が見世に出るわけではなく、三人ずつ交代による顔見世が行われたそうだ。ただし、安永三年(一七七四)の洒落本「婦美車紫鹿子」では遊女が九つの等級に分けられているが、板橋宿は中品下生、つまり中の下に評価されている。
将軍の所在が掴めないほどの大混乱に陥ったにも関わらず、略奪はほとんど発生しなかった安政の大地震
安政二年(一八五五)十月、江戸下町の隅田川地域一帯に突然に大地震が生じた。後に安政大地震といわれるマグネチュード6.9、荒川河口を震源地とする直下型大地震だ。倒壊家屋は町家およそ一万四千戸、土蔵およそ千四百棟、また焼失面積は約十四町四方。死者については定かではないが、七千人以上と推定される。家屋倒壊による圧死よりも、同時に発生した火災による被災者のほうが圧倒的多数だったともいわれている。その背景には時、幕府は財政的に貧窮しており、定火消の一部を廃止していたため防火態勢が不十分だったことも大きく影響していよう。
では、地震発生直後の大名たちはどのような様子であっただろう。安政大地震が記された「視聴草」では、こんな話が残されている。
江戸城へ真っ先に駆けつけた内藤紀伊守は、袴をはくことなく大小を差していた。その姿は大手門の門番さえも誰だかわからなかった。そこで紀伊守は番所で有り合わせの紋付きの裃を借り、どうにか登城した。続いて城中へ駆けつけた若年寄の遠藤但馬守、本多越中守もやはりまた寝間着のままであったとか。
当時の十三代将軍家定についても大奥で余震に耐えていた、あるいは完全に恐慌をきたしていたなど、話は様々だ。また、死去したとの誤報が流れた大名も少なくなかった。災害の被害が幕府の官庁街にあたる御曲輪内であったことを考慮すれば、無理のない話といえるかもしれない。
地震はその後も一か月に渡って余震が続き、有感地震だけでも百回以上を数えている。その間、市中において目立った大規模な略奪などは見られなく、わずか地震発生四日後に二例だけ記録されている。
そのひとつは、深川大島町にある札差商の倉庫が崩れた折、近くの者たちが米などを持ち出そうとしたところ、巡回中の町奉行所の同心らに発見され、その場で取り押さえられたというものだ。
もう一例は、被害をまったく受けることのなかった本所にある旗本屋敷に、地震発生以来、何も口にしていないという五、六人の罹災者が助けを求めにきた。旗本屋敷の者が追い返すと、二百人ほどの人々が抗議に押しかけたという。屋敷の家来たちは応戦しようとしたが、主人たる旗本は「追い返したのが悪かった。屋敷が揺りつぶされ、火で焼かれたと思って彼らの自由にしておけ」と命じたとのことだ。
略奪事件が少なかったのは、当時、略奪や泥棒は反道徳的との意識が強く根づいていたせいだろう。加えて災害復興をめざした救援活動が活発だったことも大きな要因だ。
ところで、この安政大地震後、震源地は常陸鹿島神宮であり、鯰が悪さをしたためだとの話が流布した。そこで地震鯰絵と称される鯰の彩色戯画が流行したという。構図としては、被災者たちが鯰を懲らしめているものが多かったそうだ。
門前町音羽とともに栄えた、桂昌院のために建てられた護国寺
綱吉が五代将軍の座に就いた翌年天和元年(一六八一)、綱吉の生母桂昌院の発願により護国寺が創建された。綱吉三十六歳、桂昌院五十五歳のときだ。開山には上野国(群馬県)碓氷八幡宮の別当大聖護国寺の住職亮賢が招かれ、幕府領地であった高田薬園を白山に移し、その跡地に堂塔が建立された。寺領三百石を賜り、天和二年(一六八二)に如意輪観音を本尊とする本堂が完成、翌天和三年(一六八三)には桂昌院の初の参詣があり、綱吉もしばしば参詣したといわれている。
この護国寺と深い関係を持つのが、やはり将軍母子の帰依を受けて隆盛を極めたことのある護持院だ。護持院は元々は現在の神田錦町にあったが、享保二年(一七一七)の大火で焼失した際、幕府は再興を認めず、護国寺と統合させている。観音堂を護国寺に、本坊を護持院とし、護持院の住職が護国寺を兼ねることになった。その後、明治維新を迎えると護持院は廃寺となり、護持院と称していた部分の堂宇は護国寺分に帰すことになった。
さて、護国寺の門前町は「京都の清水坂に似せてほしい」との桂昌院の注文を受け、門前が九丁に分けられ、桂昌院のお気に入りであった奥女中の音羽に与えられることになった。もともと一帯は門前の青柳町、桜木町とともに護国寺領三か町と呼ばれており、音羽が拝領したのは元禄十年(一六九七)のことだ。地名の由来になったのはいうまでもない。なお、昭和四十二年(一九六七)の住居表示で音羽に吸収された東青柳町、西青柳町もやはり奥女中青柳、桜木が拝領した地である。
音羽町はやがて門前町として繁栄していった。護国寺は将軍家の祈願寺となったが、庶民の町のほうは茶店や遊女屋で賑わう岡場所としての発展を見せる。岡場所とは、公許の遊里である新吉原に対し、無許可で営業する私娼窟を称した言葉だ。幕府は公娼保護の政策上、私娼売女の摘発を繰り返してはいたものの、岡場所はおよそ百六十にも及び、摘発しきれるものでもなかった。
それには音羽は護国寺、深川は富岡八幡宮、根津は根津権現の門前町であったように、岡場所のほとんどが寺社地の門前町において発達していたこととも無関係ではない。岡場所はそもそもは参詣人相手の茶屋が私娼窟へ発展したものであり、寺社の門前町の所管は町奉行所ではなく、寺社奉行であったからだ。売春行為を行っていることを把握していても、町方役人はそれを取り締まる権限を担ってはいなかった。逆にいえば、門前町は町奉行所が介入できないゆえ、私娼が集まったといえなくもない。また、同じ理由にて門前町には盗人が逃げ込んだり、博打の開帳場ともなっていたという。
が、岡場所の行きすぎた発展や私娼の増加は性病のまん延をもたらし、門前町の風紀の乱れはさすがに幕府を刺激した。そこで幕府は延享二年(一七四五)に権限を町奉行所に移管し、取締りの強化にあたっている。